仮想通貨の税金はいくらから?ビットコインの課税税率も解説
 2 mins
2 mins 仮想通貨の利益は1円から課税対象です。ただし、給与所得者など一部の人は年間20万円以下の雑所得なら確定申告が不要になる特例があります。
「仮想通貨の税金は、実際いくらからかかる?」「仮想通貨の税率は高いと聞いたけど、どれくらいかかるのだろう。」そんな疑問を抱える方も多いでしょう。
本記事では、そうした悩みを抱える投資家の皆さんに向けて、以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 仮想通貨(暗号資産)の税金・税率の仕組み
- 税負担を軽減するためにできる対策
- 仮想通貨の税金で損しないための重要ポイント
正しい知識があれば、仮想通貨の税率を恐れず戦略的に投資できます。ぜひ本記事を最後まで読み、資産を守りながら賢く増やすヒントをつかんでください。
仮想通貨(ビットコイン)の税金の最新ニュース【2026年2月】
近年、仮想通貨やビットコインの税金を見直す動きが活発化しています。投資する上での重要ポイントとなるため、定期的に最新ニュースを入手しておきましょう。
税制の見直しが加速|2028年が節目に
日本の仮想通貨(ビットコイン)税制について、申告分離課税(税率20%)への移行を視野に入れた議論が進んでいます。
政府・与党内では、仮想通貨を株式などと同様に金融商品として扱う方向性が共有されつつあり、税制面でも現行制度の見直しが重要テーマとなっています。
現状、仮想通貨取引で得た利益は雑所得・総合課税に分類されます。所得水準によっては、住民税を含めて最大55%の税率が適用される可能性があります。
こうした税負担の重さは、長年にわたり個人投資家や業界から課題として指摘されてきました。
そのため、政府・与党では、主に以下の方向性が検討されています。
- 税率を一律20%とする申告分離課税の導入
- 株式投資と同じ税制枠組みへの統一
関連する方針は「2026年度税制改正大綱」にも盛り込まれ、議論は制度設計の段階に入りつつあります。
一方で、仮想通貨を金融商品取引法の枠組みに組み込むなど、法整備との整合性が前提になります。実際の開始時期は、制度設計の進捗次第ですが、2028年1月ごろが目安と見られています。
仮想通貨(ビットコイン)の税金とは?

仮想通貨で利益が出ても、避けて通れないのが税金問題です。まずは基本的な仕組みを押さえて、何に課税されるのかを理解しましょう。
仮想通貨は雑所得に分類される
仮想通貨投資で得た利益は、所得税法上「雑所得」として扱われ、総合課税が適用されます。給与所得などと合算され、所得が多いほど税率も上がる仕組みです。
一方、株や投資信託の利益は「譲渡所得」や「配当所得」に分類され、申告分離課税が適用されます。
所得区分と課税方式の比較は以下の通り。
| 項目 | 仮想通貨 | 株式・投資信託 |
| 所得区分 | 雑所得 | 譲渡所得・配当所得 |
| 課税方式 | 総合課税(累進課税) | 申告分離課税(一律) |
| 税率 | 最大55%(所得税45%+住民税10%) | 一律約20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
| 他の所得との損益通算 | 原則不可(同じ雑所得内のみ) | 可能(譲渡所得内などで) |
| 損失の繰越控除(3年) | 不可 | 可能 |
アルトコイン取引などで得た仮想通貨の利益は、他の金融商品と比較して税金負担が高くなる傾向にあります。
特に多額の利益を得た場合には、税金に関する十分な理解と計画が不可欠です。
課税対象となる取引の種類
仮想通貨の税金は「ビットコインや草コインなどを保有しているだけ」では発生しません。課税対象となるのは、利益が確定する取引を行ったタイミングです。
代表的なケースは以下の通りです。
| ケース | 内容と課税対象 |
| 仮想通貨の売却 | 取得価格と売却価格の差額(利益)に課税(例:上場前の仮想通貨を30万で購入→50万円で売却なら20万円が課税対象) |
| 他の仮想通貨への交換 | 交換時点での時価との差額に課税(例:50万→75万円分に交換→利益25万円) |
| 商品やサービスの購入 | 仮想通貨使用時の価格と取得時の差額に課税(例:8万円→13万円相当の支払い→利益5万円) |
| マイニング報酬の取得 | 取得時の時価が収入扱い。経費(電気代など)は差し引き可 |
| 仮想通貨エアドロップ | 無料配布で取得した仮想通貨に課税(例:10万円分の仮想通貨をエアドロップで取得→雑所得として課税対象) |
これらは仮想通貨の利益が確定した時点で課税されるため、日頃から取引履歴を正確に管理し、確定申告に備えることが重要です。
特に複数の海外仮想通貨取引所を使っている方や、頻繁に売買する方は、年間を通しての仮想通貨の税金計算に注意しましょう。
仮想通貨(ビットコイン)の税率の仕組み
仮想通貨の利益は、日本の税制上「雑所得」に分類され、給与所得などと合算して課税される総合課税の対象です。
仮想通貨利益課税は累進課税方式で行われ、所得税は5%〜45%、住民税が一律10%課されるため、合計で最大55%の税率が適用される可能性があります。
確定申告が必要となるのは以下の場合です。
- 給与所得者:仮想通貨などの副業所得が年間20万円超
- 扶養に入っている学生・主婦など:所得が年間43万円超
また、仮想通貨の売買損益は以下のいずれかの方法で計算します。なお、一度選んだ方法は原則として継続適用。変更には税務署への届出が必要です。
- 移動平均法:購入のたびに取得価額を更新
- 総平均法:年間の平均取得単価を用いて損益を計算
さらに、取引手数料やブロックチェーンに関する書籍代・セミナー費用・ツール利用料など、取引に直接関連する支出は必要経費として控除可能です。これにより課税所得を抑えることができ、税負担を軽減できます。
申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科される恐れがあります。
税務署は、バイナンスジャパンやコインチェックなどの国内取引所から取引情報を把握できるため、申告漏れは発覚しやすい点にも注意が必要です。
正確な申告のためには、取引履歴の整理や損益の計算など手間がかかるため、税理士など専門家への相談も検討すべきでしょう。
仮想通貨で税金がかかるタイミング
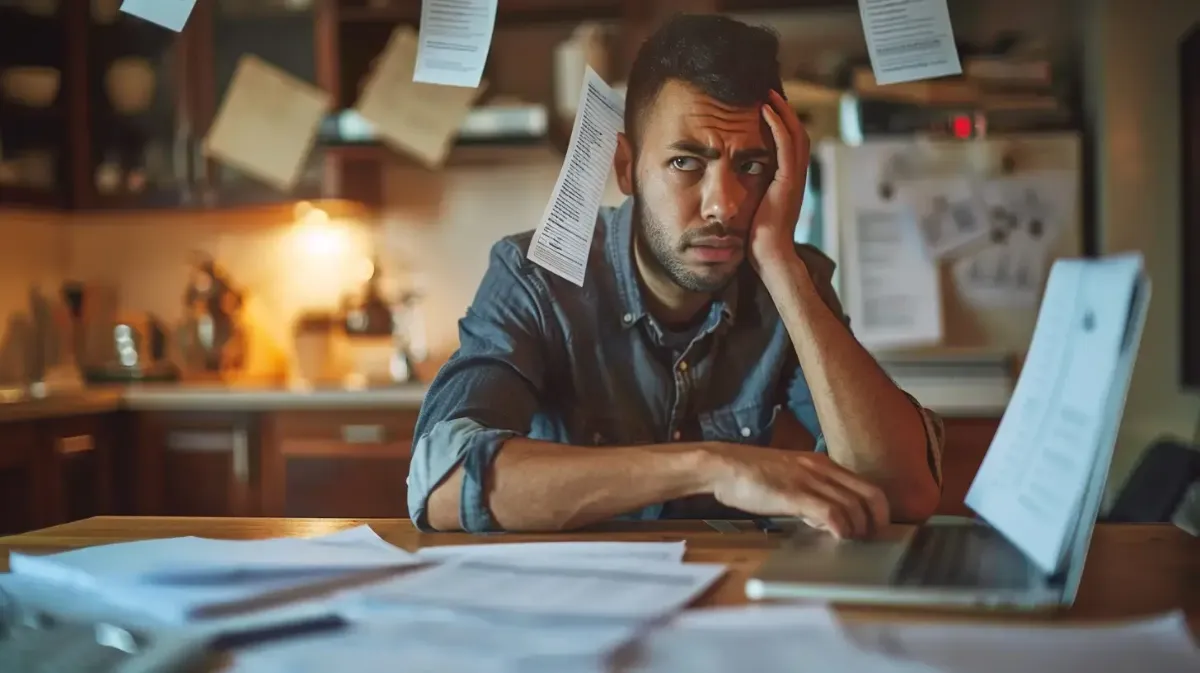
イーサリアムなどの仮想通貨は保有しているだけでは税金がかかりませんが、売買や交換、商品決済などで利益が出ると課税対象となります。
利益は原則として雑所得に分類され、給与所得などと合算して総合課税されます。会社員は年間の仮想通貨利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
BNB仮想通貨など利益が出やすいコインの納税を怠るとペナルティがあるため、税ルールを正しく理解しましょう。
売却・交換時の課税タイミング
ミームコインなどの仮想通貨を売却したり、他の暗号資産と交換した際に利益が発生すると、その利益に税金がかかります。日本円に換金していなくても、交換時の時価を基に所得が計算されます。
例えば、50万円で購入したプレセール仮想通貨が75万円になっていれば、差額の25万円が課税対象です。頻繁に交換を行うと、その都度利益が確定し課税される点に注意しましょう。
仮想通貨で決済したとき
ビットコインなどの仮想通貨を使って商品やサービスを購入する際も、支払いに用いた暗号通貨の取得時からの価格上昇分が利益とみなされ、課税所得となります。
8万円で取得した0.1BTCを13万円相当のパソコン購入に使った場合の課税所得はの以下通りです。
- 取得価格:8万円
- 決済時の価値:13万円
- 課税所得:5万円
これは、ビットコインを日本円に換金せずとも、実質的に利益が確定したとみなされるためです。
マイニングやステーキングなどで報酬を得たとき
ビットコインマイニングやステーキングで得た仮想通貨報酬は、取得時の時価を基に事業所得または雑所得として課税されます。マイニング報酬は収入とみなされ、電気代や設備費用は経費として差し引けます。
例えば、0.1BTC(時価10万円)を得て経費が5万円なら、差額の5万円が課税所得です。
日本の仮想通貨の税金制度では、取得方法によって課税のタイミングと計算方法が異なるため、自身の取引状況を正確に把握しておくことが重要です。
仮想通貨の税金はいくらから発生する?

仮想通貨をビットコインウォレットなどで持ってるだけでは税金がかかりませんが、売買・交換・決済などで1円でも利益が発生すると課税対象になります。
納税を怠るとペナルティが科されるため、爆上がり仮想通貨などで利益が出た場合に備えて、確定申告の計算方法を正しく理解しておくことが重要です。
仮想通貨の確定申告はいくらから必要?
仮想通貨の利益は原則「雑所得」に分類され、所得税(最大45%)と住民税(10%)が課される総合課税の対象です。合計で最大55%の税負担になる可能性があります。
確定申告が必要な対象者は以下の通り。
- 給与所得者:仮想通貨の利益が年間20万円超
- 学生・主婦など:仮想通貨を含む所得が年間43万円超
課税対象となる利益の発生タイミングは次の通りです。
| 取引内容 | 例 | 課税所得の計算例 |
| 仮想通貨の売却 | 30万円で購入→50万円で売却 | 50万円−30万円=20万円 |
| 仮想通貨の交換 | 50万円相当のビットコインを75万円相当の別資産に交換 | 75万円−50万円=25万円 |
| 商品やサービスの購入 | 取得価格と決済時の価値の差額が課税対象 | — |
| マイニングなどの取得 | 取得時点の時価で所得計算 | — |
日本円に換金していなくても、仮想通貨同士の交換や決済で利益が確定し課税されるため、注意が必要です。
確定申告書の作成手順と記入方法
仮想通貨の確定申告は複雑なため、期限前に余裕をもって準備しましょう。主な手順は以下の通りです。
- 年間取引履歴の集計:各取引所から取引報告書や履歴をダウンロードし、売却価格・購入価格・数量・手数料などを確認する。
- 所得の分類と計算:売却益、交換取引、マイニング・ステーキング収入を分類。
課税対象額は総収入から必要経費(取引手数料、通信費の一部、取引ツール使用料など)を差し引いた金額。 - 確定申告書の作成:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や市販の会計ソフトを利用。
会計ソフトを使えば、収入や経費を入力するだけで申告書を自動作成でき、作業が大幅に楽になるため、ぜひ活用しましょう。
提出時の必要書類と注意事項
確定申告書の提出期間は毎年2月16日から3月15日までです。提出方法は、以下の選択肢があります。
- 税務署への直接提出
- 郵送
- 24時間利用可能なe-Taxによるオンライン申告(青色申告の場合は控除額が増えます)
申告を怠ると無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されます。税務署は仮想通貨取引所に対して調査権限を持つため、必ず期限内に申告しましょう。
納税も3月15日までに完了させる必要があり、方法は以下のものがあります。
- 銀行窓口・ATMでの振込
- インターネットバンキング
- e-Taxの口座振替
- クレジットカード払い(ポイント獲得可能)
- コンビニ支払い
仮想通貨投資で利益が出たら納税分を別に保管し、計画的に再投資することをおすすめします。
仮想通貨の税金計算の方法
仮想通貨の利益にかかる税金は、株式投資やFXとは異なり、利益が大きくなるほど税率が上がる累進課税が適用されます。
具体的には、仮想通貨利益に対し所得税率が最大45%に住民税10%が加わり、最大で55%の税率が適用される可能性があります。
取得価額の計算方法(移動平均法・総平均法)
仮想通貨の売買損益は、「移動平均法」か「総平均法」のいずれかで取得価額を計算します。
- 移動平均法:仮想通貨を購入するたびに、その時点での購入額と残高を平均して所得を計算
- 総平均法:1年間の購入平均レートをもとに総購入金額を算出し、売却合計金額との差額を所得として計算
一度選んだ方法は原則継続適用が必要で、変更する場合は翌年3月15日までに税務署へ「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書を提出し承認を得る必要があります。
ビットコインの税金計算の流れ
ビットコインなどの仮想通貨税金計算は以下の流れで行います。
- 年間(1月1日~12月31日)の取引履歴を集計し、売買価格や数量、手数料を確認
- 売却益、交換益、マイニング・ステーキング報酬など所得の種類を分類
- 総収入から取引手数料や通信費、取引ツール使用料などの必要経費を差し引いて利益額を算出。
給与所得者は利益が年間20万円以上、扶養されている学生や主婦は43万円以上で確定申告が必要です。
例えば、給与500万円に仮想通貨の利益50万円が加わる場合、合算所得から控除を引いた課税所得に応じて所得税が課されます。仮想通貨の税金計算は複数のステップを踏むため、正確な記録と理解が重要です。
仮想通貨税の合法的な節税対策4選

仮想通貨の取引で得た利益には税金がかかりますが、適切な知識と対策を講じることで、合法的に税負担を軽減することが可能です。
ここでは、仮想通貨の税金を節税するための具体的な方法を4つご紹介します。
①:売却タイミングを分散して所得を抑える
仮想通貨の税金は、利益が確定した時点で発生します。仮想通貨を長期保有し、売却するまでは課税されません。
具体的には、他の仮想通貨に交換した場合、仮想通貨で商品・サービスを購入した場合、仮想通貨を売却して日本円に換金した場合などに税金がかかります。多額の利益を一度に確定すると、高い税率が適用されやすくなります。
対策としては、仮想通貨の売却タイミングを分散し、所得・税金を抑える方法があります。給与所得者の場合、年間20万円以下の利益であれば原則として確定申告は不要です。
この非課税枠を活用し、利益を複数年に分散させることで、税率を低く抑え、税負担を軽減できます。
②:必要経費をもれなく計上する
仮想通貨の所得は、「取引による総収入額から必要経費を差し引いた金額」で計算されます。経費を正しく計上することで、課税対象となる所得を減らし、税負担を軽くすることが可能です。
経費として認められる主なものは以下の通りです。
これらを適切に計上するには、領収書や支出記録を日常的に保管しておくことが重要です。経費を正しく申告することで、課税所得を圧縮し、納税額を抑えることができます。
③:損益通算を活用する
仮想通貨取引で損失が出た場合は、同じ年内の他の仮想通貨取引の利益と相殺する「損益通算」が可能です。たとえば、仮想通貨Aで20万円の損失、仮想通貨Bで30万円の利益があれば、差し引き10万円が課税対象となります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 仮想通貨の損失は、FXなど他の雑所得とは通算不可
- 「損失の繰越控除」は仮想通貨には適用されない
損失が出た年には他の仮想通貨の利益と相殺することが重要です。「ビットコインの確定申告はいくらから?」と悩む方も、適切な損益通算で課税所得を減らし、税負担を軽減できます。
④:iDeCoやふるさと納税などの所得控除を活用する
仮想通貨の利益を含む総所得から所得控除を活用することで、課税所得を減らし、税負担を軽減できます。特に節税効果が高い制度は以下のとおりです。
| 制度名 | 概要 | 節税効果 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金が全額所得控除対象。運用益も非課税で再投資される | 所得税・住民税の軽減、老後資金形成にも有効 |
| ふるさと納税 | 寄付額のうち2,000円を超える部分が控除対象。返礼品も受け取れる | 所得税・住民税から控除(上限あり) |
これらをうまく活用することで、ビットコインの税金を合法的に抑えることが可能です。暗号資産の税金対策として、確定申告前に検討しておくと良いでしょう。
仮想通貨の税金に関するリスク・注意点
仮想通貨の利益は少額でも条件次第で課税対象となり、申告漏れには重いペナルティが科される可能性があります。
取引所からの情報提供により、税務署は取引内容を把握できるため、「バレない」と考えるのは危険です。正確な申告と期限内の対応が不可欠です。
利益が20万円を超えたら確定申告が必要
会社員など給与所得者が仮想通貨で利益を得た場合、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。この基準は仮想通貨に限らず、副業やフリマアプリの収入にも適用されるものです。
仮想通貨利益が20万円以下である場合は原則として所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる自治体もあるため注意が必要です。
一方、扶養されている学生や専業主婦など、給与所得のない人は43万円を超えると課税対象となります。少額でも継続的に取引している場合は、自分の所得状況を早めに確認しておくことが大切です。
確定申告の期限を絶対に守ること
仮想通貨の確定申告期限は、他の所得と同様に毎年2月16日〜3月15日です。期限を過ぎて申告すると、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課される可能性があります。
近年は国税庁による仮想通貨取引の調査も強化されており、過去の取引履歴を遡って確認されるケースもあります。
仮想通貨の取引履歴は複雑になりやすく、申告準備には時間がかかるため、早めの対応が重要です。
年間取引報告書の取得や履歴の整理は余裕をもって行いましょう。会計ソフトの活用や税理士への相談も有効な手段です。
まとめ
本記事では、仮想通貨の税金について詳しく解説しました。
現行制度では、仮想通貨取引の利益は原則として雑所得(総合課税)に分類されます。所得状況によっては、住民税を含めて最大55%の税率になる可能性があり、税負担と計算の手間が課題になりやすい点は押さえておきましょう。
ただし、仮想通貨税制改正として、仮想通貨取引を申告分離課税(税率20%)へ見直す方向性も示されています。とはいえ、法整備などを前提とするため、開始時期や対象範囲は今後変わる可能性があります。
税制は変わりやすい分野です。一次情報を確認しつつ、取引履歴の管理と損益計算を早めに進め、冷静に対応していきましょう。
仮想通貨の税金に関してよくある質問
仮想通貨で50万円儲けたら税金はいくらですか?
仮想通貨をほったらかしにしておくと税金は発生しますか?
ビットコインで1000万円稼いだら税金はいくらですか?
参考情報
Coinspeakerの実績
月間ユーザー
記事・ガイド
調査・研究時間
執筆者
 監修者:
監修者:
井上 雪芽
Coinspeakerアナリスト, 99 postsCoinspeakerアナリスト。2020年から仮想通貨投資を始め、ビットコイン、NFT、DeFiへの投資経験がある。2025年6月にCoinspeakerに加わる。